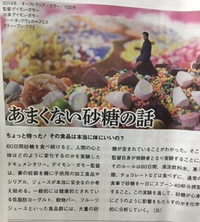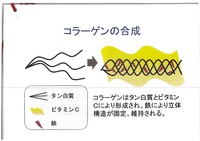2009年05月13日
糖尿病の投薬
先日、身内の健康相談を受けました。
50歳代女性 既往歴なし 手術歴なし
今年3月中旬に某病院で人間ドックの結果についての相談でした。
空腹時血糖 107
HbA1c 6.1
コレステロール 279
HDL コレステロール 76
中性脂肪 86
GOT 22
GPT 16
コリンエステラーゼ 407
脂質代謝異常、糖代謝異常を指摘され、同病院の外来を予約され受診しました。
そして、初回受診時に
経口糖尿病薬 SU剤(スルフォニルウレア系) アマリール錠が処方されました。
身内にドクターがいて相談したところ
(低血糖をおこす危険があるので内服は好ましくない)と言われたとのことです。
ご本人は(強い薬なのでは・・)と心配しています。
強い薬かどうかの前に・・
空腹時血糖 107、HbA1C 6.1は糖尿病治療薬の適応なのでしょうか・・・。
投薬の前に、去年より2~3kg増加しているという体重を是正するような保健指導がなされたのでしょうか・・。
受診時は緊張していたが、生活指導のことは聞いていない気がすると・・。
そして、経口糖尿病薬を処方する前に、糖尿病のきちんとした検査さえ行っていない。
食後高血糖がないかどうか、自前のインスリンはきちんと出ているのか・・。
特定検診(メタボ検診)が始まった頃、保健師の友人との話が思い出されます。
『肥満や、脂質代謝異常、糖代謝異常で要指導で病院受診された場合、病院それぞれでの対応が問題。
医療機関により指導にあたるスタッフの確保、知識・技術には格差があるため、煩雑な外来では医師による保健指導もままならず、結局は投薬するケースが多くなるのでは・・・』
と・・・。
「強い薬」の表現には当てはまらないとおもいますが
食生活、運動療法でコントロールできると思われる軽度の高血糖に、経口糖尿病薬を内服すれば低血糖におちいる危険はあります。
また、くすりの種類にも問題があります。
グリミクロン、オイグルコン、ダオニール、パミルコン、そしてアマリール・・・これらのくすりは経口糖尿病薬で最も多く処方されている、SU剤(スルホォニルウレア系)です。
このSU剤は膵臓に働きかけインスリンの分泌を促し、血糖値を下げる作用があります。
インスリンが過剰に出ていても、「もっと出せ~」と働きかけ膵臓を酷使します。
肥満や内臓脂肪蓄積の場合、インスリン抵抗性がおこり高血糖になります。
インスリン抵抗性とは、インスリンホルモンは出ているが、効きが悪いため量を多く出しカバーしょうとする。
つまりは、いつもインスリン過剰分泌になっていることが考えられるにもかかわらず、SU剤によりますます過剰に分泌される。。
インスリンホルモンは別名『中性脂肪合成ホルモン』です。
インスリンホルモンが出れば出るほど肥満・内臓脂肪蓄積の一途にあるのです。
そして、インスリンホルモンにも在庫の限りがあります。
過剰に分泌され、底をついたとき本当の糖尿病になります。
栄養療法では、肥満の人へのSU剤は禁忌としています。
(内服している限り減量が難しいから)
糖尿病と診断し投薬を始める前に、せめて自前のインスリンホルモン(血液検査でCペプチド)を計ってほしいです。
そして食後の血糖値、インスリンホルモンの経過を糖負荷試験(出来れば5時間ー通常の医療保険ではおこなっていません)を行ってほしいです。
そして、その結果に基づいて、投薬が必要なら薬の選定をしてほしいです。
1年前ですが、これも身内の方の外来に付いていき
『お薬を変えてほしい』と、主治医に頼んだことがあります。
上記の様なことは喋らず、『伯母さんにはこの薬はあっていない様なので・・』と
そしたら、SU剤は続投で、ベイスン(食後過血糖改善薬)が追加されました。
・・・・難しいです。
今回相談のあった女性は、近日分子栄養医学が薦める項目で検査予定です。
また機会がありましたら、糖尿病のデーターについて、インスリン過剰分泌の改善の対策について。。
50歳代女性 既往歴なし 手術歴なし
今年3月中旬に某病院で人間ドックの結果についての相談でした。
空腹時血糖 107
HbA1c 6.1
コレステロール 279
HDL コレステロール 76
中性脂肪 86
GOT 22
GPT 16
コリンエステラーゼ 407
脂質代謝異常、糖代謝異常を指摘され、同病院の外来を予約され受診しました。
そして、初回受診時に
経口糖尿病薬 SU剤(スルフォニルウレア系) アマリール錠が処方されました。
身内にドクターがいて相談したところ
(低血糖をおこす危険があるので内服は好ましくない)と言われたとのことです。
ご本人は(強い薬なのでは・・)と心配しています。
強い薬かどうかの前に・・
空腹時血糖 107、HbA1C 6.1は糖尿病治療薬の適応なのでしょうか・・・。
投薬の前に、去年より2~3kg増加しているという体重を是正するような保健指導がなされたのでしょうか・・。
受診時は緊張していたが、生活指導のことは聞いていない気がすると・・。
そして、経口糖尿病薬を処方する前に、糖尿病のきちんとした検査さえ行っていない。
食後高血糖がないかどうか、自前のインスリンはきちんと出ているのか・・。
特定検診(メタボ検診)が始まった頃、保健師の友人との話が思い出されます。
『肥満や、脂質代謝異常、糖代謝異常で要指導で病院受診された場合、病院それぞれでの対応が問題。
医療機関により指導にあたるスタッフの確保、知識・技術には格差があるため、煩雑な外来では医師による保健指導もままならず、結局は投薬するケースが多くなるのでは・・・』
と・・・。
「強い薬」の表現には当てはまらないとおもいますが
食生活、運動療法でコントロールできると思われる軽度の高血糖に、経口糖尿病薬を内服すれば低血糖におちいる危険はあります。
また、くすりの種類にも問題があります。
グリミクロン、オイグルコン、ダオニール、パミルコン、そしてアマリール・・・これらのくすりは経口糖尿病薬で最も多く処方されている、SU剤(スルホォニルウレア系)です。
このSU剤は膵臓に働きかけインスリンの分泌を促し、血糖値を下げる作用があります。
インスリンが過剰に出ていても、「もっと出せ~」と働きかけ膵臓を酷使します。
肥満や内臓脂肪蓄積の場合、インスリン抵抗性がおこり高血糖になります。
インスリン抵抗性とは、インスリンホルモンは出ているが、効きが悪いため量を多く出しカバーしょうとする。
つまりは、いつもインスリン過剰分泌になっていることが考えられるにもかかわらず、SU剤によりますます過剰に分泌される。。
インスリンホルモンは別名『中性脂肪合成ホルモン』です。
インスリンホルモンが出れば出るほど肥満・内臓脂肪蓄積の一途にあるのです。
そして、インスリンホルモンにも在庫の限りがあります。
過剰に分泌され、底をついたとき本当の糖尿病になります。
栄養療法では、肥満の人へのSU剤は禁忌としています。
(内服している限り減量が難しいから)
糖尿病と診断し投薬を始める前に、せめて自前のインスリンホルモン(血液検査でCペプチド)を計ってほしいです。
そして食後の血糖値、インスリンホルモンの経過を糖負荷試験(出来れば5時間ー通常の医療保険ではおこなっていません)を行ってほしいです。
そして、その結果に基づいて、投薬が必要なら薬の選定をしてほしいです。
1年前ですが、これも身内の方の外来に付いていき
『お薬を変えてほしい』と、主治医に頼んだことがあります。
上記の様なことは喋らず、『伯母さんにはこの薬はあっていない様なので・・』と
そしたら、SU剤は続投で、ベイスン(食後過血糖改善薬)が追加されました。
・・・・難しいです。
今回相談のあった女性は、近日分子栄養医学が薦める項目で検査予定です。
また機会がありましたら、糖尿病のデーターについて、インスリン過剰分泌の改善の対策について。。
Posted by yunnta at 00:11│Comments(1)
│健康
この記事へのコメント
yunntaさん、 こんにちは。
健康と医療に関わる問題提起、ありがとうございます。
一般には、『いのち』の仕組み構造を知識として持っている人は少ないのでしょう。
各自で感じ方はことなりますが,体が何か普通じゃない状態(病気)を感じるときに『健康』を意識するのです。
そして、医師の診断を受け,その診断結果で対処療法がはじまるのです。
そのときに、せめて健康でないところの説明を科学的診断にもとづいて受けたいものです。
その結果、対処療法のメリット&デメリットを知らせていただきたいものです。
医師の忙しい日常は理解していますが、病んでる人にたいしては、それなりの科学的データ-に基づく親切診断,治療を願うものです。
yunntaさんとの出会いから、病気になる前から,『いのち』の基本機能を学び、自分の健康知識は自分で学ぶ機会を持つことが大切なことを教えていただきました。
何事も,自分の行動で可能なことから始めることが大切なのでしょう。
yunntaさんの『健康カウセラー』の知識を、多くの方がお仕事として認め、そのサービスを受ける意識から『健康知識』が普及することと確信しています。
その『健康知識』を意識して,毎日の生活の中で生かすことが健康行動なのでしょう。
いつもながら、健康のお話、感謝しています。
健康と医療に関わる問題提起、ありがとうございます。
一般には、『いのち』の仕組み構造を知識として持っている人は少ないのでしょう。
各自で感じ方はことなりますが,体が何か普通じゃない状態(病気)を感じるときに『健康』を意識するのです。
そして、医師の診断を受け,その診断結果で対処療法がはじまるのです。
そのときに、せめて健康でないところの説明を科学的診断にもとづいて受けたいものです。
その結果、対処療法のメリット&デメリットを知らせていただきたいものです。
医師の忙しい日常は理解していますが、病んでる人にたいしては、それなりの科学的データ-に基づく親切診断,治療を願うものです。
yunntaさんとの出会いから、病気になる前から,『いのち』の基本機能を学び、自分の健康知識は自分で学ぶ機会を持つことが大切なことを教えていただきました。
何事も,自分の行動で可能なことから始めることが大切なのでしょう。
yunntaさんの『健康カウセラー』の知識を、多くの方がお仕事として認め、そのサービスを受ける意識から『健康知識』が普及することと確信しています。
その『健康知識』を意識して,毎日の生活の中で生かすことが健康行動なのでしょう。
いつもながら、健康のお話、感謝しています。
Posted by 白州の爺や at 2009年05月15日 16:13
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。